東京パラスポーツスタッフ認定者インタビュー(3)ボッチャ・トレーナー 前野香苗さん(2019/2/18)
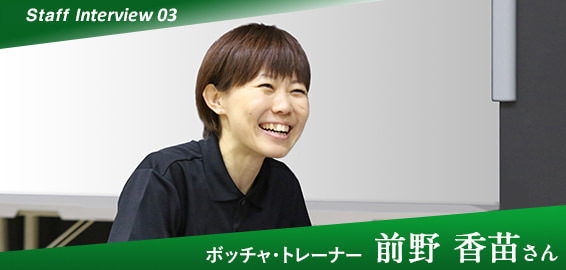
- まえの・かなえ 1984年生まれ。株式会社スポーツセンシング所属。
- 理学療法士として小児のリハビリテーションに携わる中、2013年からトレーナーとして、ボッチャの日本代表強化合宿に参加し、その後も数多くの国際大会に帯同。ボッチャやパラスポーツの選手サポートに注力している。
パラスポーツ選手たちのコンディショニングケアやトレーニング指導、生活介助などのサポートを行う「トレーナー」。ボッチャに魅了され、トレーナー・理学療法士として選手たちを支える前野香苗さんにインタビューしました。
「選手のそばにいるトレーナーだからこそ寄り添ったサポートを心がける。」
『海外遠征ではハプニングを楽しむぐらいの気持ちで。』
~ボッチャのトレーナーとは、どのような役割なのでしょうか。~
メインは体のコンディショニングケアで、ベストな状態で試合に臨めるように体の状態を整えていきます。あとはトレーニング方法を考えたり、投球動作を見ながら体の使い方や姿勢についてアドバイスをしたりします。(特に障害の程度が重い選手の多いボッチャの)特別な所として、生活介助も大きな役割です。トイレ、お風呂、お食事、着替え、あらゆる所に介助が必要な選手たちなので、サポートに入り日常の動きを見ていると、その日のコンディションが分かったりします。選手たちがストレスを溜めることなく生活が送れるよう、介助の中でなるべく選手に余計な負担(気疲れなど)をかけないように気をつけています。
~トレーナーとして関わるようになったのはいつ頃ですか。~
10年ほど前、小児施設で理学療法士として働いていた頃、ボッチャ日本選手権大会のフィジオサポートに参加したことがきっかけです。最初は、普段リハビリで関わっている子供たちにボッチャなどスポーツの楽しみを知ってもらいたいという思いが主でしたが、続けているうちに競技としての面白さに引き込まれました。それから選手たちのサポートをしたいと思い、ロンドン2012パラリンピックの後、2013年頃から日本代表強化合宿への参加や、海外遠征への帯同など本格的にトレーナーとして活動するようになりました。
~体力的に大変なこともありそうですが、いかがでしょうか。~

遠征に行くと、タイムスケジュールの制限が多くなります。
基本は選手達と泊まり込みで生活を共にするのですが、1日の流れとしては、起床から生活介助が始まり、競技会場に行けば試合に向けたコンディショニングやアップ、宿舎に戻れば食事・入浴などの生活介助、就寝前にクールダウン、選手が就寝してからスタッフはミーティングを行います。私たちが就寝する頃には日付が変わっていて、翌日は4時から5時頃に起きるみたいな感じです(笑)。国内での合宿では2泊程度ですが、海外遠征だと、これが1週間から2週間続くので、体力勝負ですね。
また、一筋縄ではいかないのが遠征です。それこそハプニングはつきもので、まずフライトからいろいろな対応が必要になります。重度の障害がある選手の中には、人工呼吸器を付けている選手や、自力で姿勢を保つ事が難しい選手もいるので、自身の車椅子を預けてから、どうやって飛行機に乗り込み、フライト中の姿勢設定をどうするのかなど、本人やスタッフと打合せをします。車椅子は競技にも使用する大切な用具なので、念入りに梱包した上で、輸送をお願いするのですが、荷物が紛失したり、破損することもあり、「車椅子が届かない! 次の便で届きます。」ということもこれまでにありました(笑)。選手たちが動揺してしまわないように、ハプニングをどれだけ余裕を持ちながら楽しめるか、それぐらいの気持ちでいます。
現地に行って一番困るのが、お風呂やトイレといった水回りで、日本に比べると設備が行き届いていない所が多いです。宿舎や競技会場に着いたら、まずは動線や設備を確認し、少しでも選手がリラックスして過ごすことができ、且つ私たちの介助負担も少ないように工夫していきます。あと、現地の食事が合わない場合があるので、常に日本食のレトルト食品等も用意して、エネルギー補給はもちろんですが、日本の味で選手たちの気持ちをほぐせるようにしています。
また、競技会場への移動1つとっても、どのような車で車椅子を何台乗せられるかなどの条件により、一度に移動できる選手の人数が限られてくるため、それによってスタッフの配置や選手のケアのスケジュールも変わってきます。早朝の試合の場合、時間を節約するために車内でケアをしようとか、宿舎でテーピングをしてから向かおうとか、パラスポーツならではのタイムスケジュールで、これが遠征の醍醐味であり、大変な所かなと思います(笑)。
『仕事の疲れは仕事でリフレッシュ。』
~理学療法士とトレーナーの両立はどのようにされていますか。~
昨年度まで、本業の理学療法士として、平日5日は職場に勤務し、土日は合宿や練習会に参加していました。でも、年3回程ある遠征に参加するには有給休暇だけでは足りず、恵まれた職場だったので「休んでもいいよ」と許していただいていました。しかし、欠勤が増えることや役職的にも申し訳なく思ってしまい、今年度から非常勤勤務になり、様々な方のご協力でトレーナーとして動きやすい体制に変えることができました。愛知から関東に単身で引っ越して、今は東京2020パラリンピックに向けて、スタッフとしての活動に力を入れています。
~仕事や競技サポートに疲れた時、どのようにリフレッシュしていますか。~

私は仕事が好きなので、仕事の疲れは仕事でリフレッシュします(笑)。競技サポートでは大人との関わりが多いので、本業の小児のリハビリでは子供たちとのふれあいの中で癒されています。また、時間が空いている時には、トップ選手に失礼を承知で「試合してよ」と挑み対戦してもらいますが、まったく勝てません(笑)。そうやってリフレッシュしています。数少ない休日は、ひたすら寝ています。休める時には休み、体力を回復させるのが鉄則です。
~トレーナーとして心掛けていることはありますか。~

私が心掛けているのは、決して戦術面や試合内容に関わるところはコーチングしない事です。
コーチもトレーナーも選手をサポートする仲間ですが、それぞれの役割分担はしっかりしようと考えています。
トレーナーは、体のコンディションを整えるのがメインの仕事ですが、競技にベストな状態で臨むには、選手の「心」のコンディションも整っていて初めて、試合で力を発揮できると思っています。遠征時のクールダウンでは、少し長めに時間を取って、選手が試合で感じた事や考えた事などゆっくりと話してもらいながら、その日の体の調子だけでなく気持ちの状態も把握し、選手に身近な立場として、寄り添いながら必要なサポートをしていく事を一番心掛けています。
『スタッフは、時として「家族」であり「同志」である存在。』
~「東京パラスポーツスタッフ」に認定されて、どのようなお気持ちですか。今後の意気込みなどもお願いします。~
たくさんのパラスポーツがあって、さらに、数多くのスタッフがいる中で認定していただいた事はとても嬉しいです。スタッフにスポットライトを当てていただける機会もなかなか無いので、パラスポーツやボッチャのいい所を情報発信したいと思っています。
~「スタッフ」とはどういう存在だと考えていますか。~

ボッチャの場合、衣食住を共にすることもあって、特に選手との距離が近いと感じています。選手たちは、日常では介助されることが多い立場ですが、コートに入れば「選手」が主体となり、輝ける場だと思っています。その中でスタッフは、ある場面では家族に近い存在であり、競技の場面では共に戦う同志でもあり、どのような場面でも選手と並走していける存在であればと思います。
~ボッチャの魅力を教えてください。~
ボッチャは、「相手のボールよりも自分のボールが白い目標球に近ければ勝ち」というシンプルなルールと、将棋や囲碁みたいに相手の先を読んで戦術を考える奥深い面が魅力です。観戦するのも面白いですが、実際にやってみると本当に楽しいスポーツなので、是非皆さんにも体験して欲しいです。チーム戦で面白いのは、攻め方などに選手個々の性格が出るところです。仲間とコミュニケーションを取りながら戦術を組み立てていくので、仲間と一緒にプレイする面白さも魅力です。
~この記事を読んでボッチャをやってみたい人がいたら、どうすればいいでしょうか。~

最近は地域の特別支援学校や障害者スポーツセンター等にボッチャボールを置いてある施設が増えていますので、近隣の施設に問い合わせていただくのがいいかと思います。各地にボッチャ協会も発足してきており、体験会も頻繁に開催されているので、ぜひ参加してみて下さると嬉しいです。
~東京2020パラリンピックを目指す選手へ期待していること、応援のエールをお願いします。~
ボッチャ日本代表がリオ2016パラリンピックのチーム戦で銀メダルを獲得してから2年になります。2018年8月の世界選手権では、世界ランキング1位のタイ代表チームに負けてしまいましたが、選手の皆さんの日々の努力で力の差はないと感じられます。国内大会でも選手の力はレベルアップしているように見受けられ、選手同士が良きライバルとして切磋琢磨しながら、2020に向けてスキルアップしてほしいなと思います。やはり自国開催というところで気負いもあると思いますが、選手自身が守りに入らず、常に挑戦する心を持って突き進んで欲しいと思いますし、その選手たちをしっかりとサポートできるように私も頑張りたいと思います。
選手がベストなコンディションで試合を迎えられるようにと、前野さんは、いつでも笑顔で選手たちに語りかけながらケアを行っています。その笑顔に、選手たちもちょっとキツめのストレッチにも「痛い」とは言えないのだとか。体のケアのみならず、選手たちの気持ちもリラックスさせる前野さんでした。